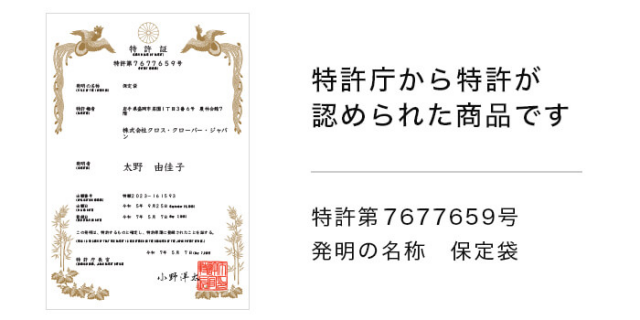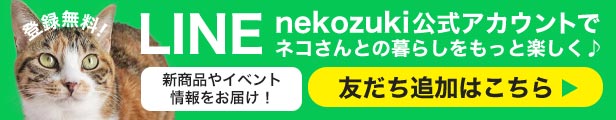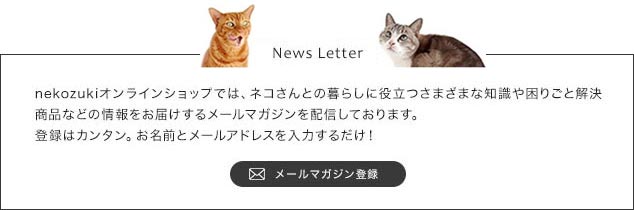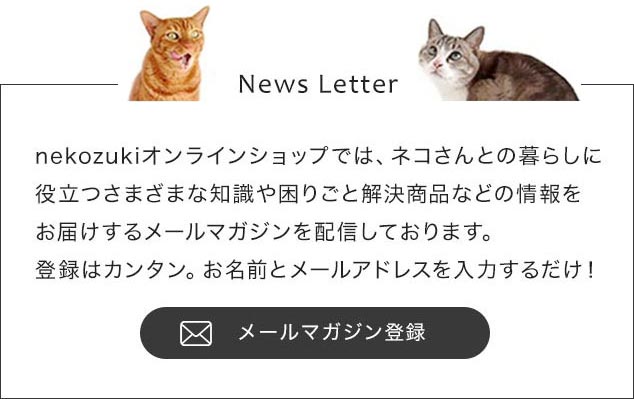最近、ネコさんが水をよく飲むようになった

おしっこの様子がいつもと違う気がする……。
もしかしてうちのネコさん、腎臓病かも?と不安に感じていませんか。
ネコさんに多い慢性腎臓病(CKD)は、初期症状が見逃されやすく、気づいたときには進行していることも少なくありません。
本記事では、獣医師の佐藤れえ子先生の講義をもとに、ネコさんの慢性腎臓病について症状から原因、治療法、予防までを詳しく解説します。
大切なネコさんと1日でも長く健やかな毎日を送るために、今日からできることを一緒に確認していきましょう。
佐藤れえ子先生に腎臓病について詳しく解説していただきました。全5本の動画になっています。ぜひご覧下さい。
▼解説動画はこちら
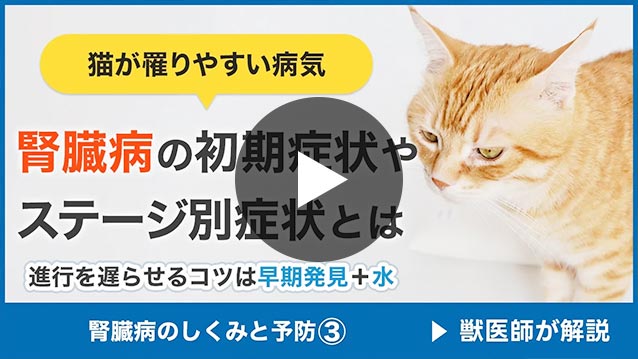
- ネコさんの腎臓病について知りたい
- ネコさんの腎臓病の原因を知りたい
- ネコさんの腎臓病の治療法を知りたい
- ネコさんが腎臓病かもしれないと不安を抱いている
- 腎臓病を予防するには何をしたらよいか知りたい
この記事の目次
猫の腎臓病とは?
ネコの腎臓病には、「急性腎障害(AKI)」と「慢性腎臓病(CKD)」の2種類があります。
| 種類 | 特徴 | 原因例 |
| 急性腎障害(AKI) | 急激に腎機能が低下する | 中毒、感染症、外傷、腎結石 など |
| 慢性腎臓病(CKD) | 少しずつ腎機能が失われていく進行性の疾患 | 加齢、遺伝的要因、過去の腎疾患など |
なかでも「慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)」は、ネコさんの罹患率が高く、とくに高齢のネコさんにおいては非常に多く見られる疾患のひとつです。
 佐藤れえ子先生
佐藤れえ子先生 最新の論文ではネコさんのおよそ35%がCKDを患い、15歳以上の発症率は80%を超えるという報告もあります。
「CKD」は病名ではない!?慢性腎臓病の定義
CKDとは、さまざまな原因によって腎臓の機能が進行性に徐々に失われていく病気で、3ヶ月以上腎障害が続く状態を指します。
病名というよりは「状態」を表すもので、原因が何であれ、腎臓に慢性的なダメージがある場合に、慢性腎臓病(CKD)と診断されます。
個々の病気自体は異なっていても、腎臓病としての症状の出方や悪くなり方は同じような傾向を示すのが特徴です。
さまざまな役割を果たす腎臓
腎臓には以下のような役割があります。
- 老廃物のろ過と排出(尿の生成)
- 造血ホルモン「エリスロポエチン」の産生
- 血圧の調節
- ビタミンDの代謝
腎臓は、体内の老廃物をろ過し、尿として排出する重要な臓器です。そのほかにも、血圧の調節やビタミンDの代謝など、生命の保持に欠かせないさまざまな役割を果たしています。
 佐藤れえ子先生
佐藤れえ子先生 腎臓は尿をつくるだけでなく、さまざまな重要な機能を担っています。CKDの進行によって、貧血や高血圧などの症状が出てくるのはこのためです。
腎臓の機能が落ちるとどうなる?
腎臓の機能が低下すると、以下のようなさまざまな問題が体に現れてきます。
- 尿がうまく濃縮されず、薄い尿を出し、大量に水を飲む(多飲多尿)
- 老廃物が体内に溜まり、尿毒症の症状がみられる(食欲低下、吐き気、口臭など)
- 貧血や高血圧など、全身への影響も
慢性腎臓病のステージ分類について
国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS)のガイドラインでは、ネコの慢性腎臓病(CKD)を4つのステージに分類しています。
この分類は、おもに血液中のクレアチニン値とSDMA(対称性ジメチルアルギニン)値をもとに行われ、病気の進行度を把握する目安として活用されます。
| ステージ | 特徴 | 主な症状・検査所見 |
| ステージ1 | クレアチニンは正常値内(<1.6 mg/dL)、SDMAの軽度上昇や画像診断などで腎障害の兆候が見られる | 自覚症状はほとんどない。尿比重の低下や微量のタンパク尿など軽微な異常が見られることも |
| ステージ2 | クレアチニンがやや上昇(1.6〜2.8 mg/dL)、SDMAもやや上昇 | 多飲多尿など軽度の症状が見られ始める。臨床的にはまだ比較的安定 |
| ステージ3 | クレアチニンが中等度に上昇(2.9〜5.0 mg/dL)、SDMAは大幅上昇(26~38 μg/dL) | ステージ3末期では、食欲低下、嘔吐、体重減少、貧血などの症状が明確に現れる。合併症(腎性貧血、高血圧、骨疾患など)のリスクが高まる |
| ステージ4 | クレアチニンが高度に上昇(>5.0 mg/dL)、SDMAも高値(>38 μg/dL) | 尿毒症の症状が強く現れ、命に関わる状態。尿毒症クリーゼのリスクも増加。集中治療や腎代替療法の検討が必要になる |
- 血液検査 - クレアチニン:腎機能の代表的な指標
- 尿検査(尿比重・蛋白尿):濃縮機能や腎臓からの尿蛋白の漏れを確認
- 画像検査(エコー・レントゲン):腎臓の形状や萎縮、結石の有無などを確認
- SDMA(対称性ジメチルアルギニン):より早期の腎機能低下を検出できる新しいマーカー
※ステージ分類は、あくまで病態の“進み具合”を表すものであり、診断名ではありません。腎疾患の診断にはSDMAやクレアチニンの値だけでなく、尿検査、画像診断、臨床症状などを総合的に判断して行われます。その上で、症例が慢性腎臓病のどの程度の段階にいるのかをステージ分類表に当てはめて判断します。

ネコさんの腎臓のつくりやはたらき、ステージ分類について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
猫の慢性腎臓病の症状

ネコの慢性腎臓病(CKD)は、進行度によって症状が異なります。ここでは、初期から末期までの代表的な症状をご紹介します。
猫の慢性腎臓病の初期症状
初期の慢性腎臓病では、目立った症状が見られない場合がほとんどです。しかしながらステージ1~2のネコさんには、次のようなサイン(臨床症状)が見られることもあります。
- 水をよく飲む(多飲)
- おしっこの量が増える(多尿)
- 運動量が減る
 佐藤れえ子先生
佐藤れえ子先生 ネコさんがお水をたくさん飲むことは良いことですが、突然たくさん飲むようになり、かつ薄い色のおしっこを多く出すようになったときは要注意のサインです。
また、ステージ2まで進行すると、運動量が落ちる症状が見られることもありますが、室内飼いのネコさんはもともと運動量が少ないこともあり、変化としてはわかりづらいかもしれません。
日々ネコさんを観察し、わずかな変化を見逃さないこと、また定期健診を受けてネコさんの健康状態をこまめに把握することも大切です。
猫の慢性腎臓病の末期症状
ステージ3~4まで病気が進行していくと、次第に以下のような症状が現れてきます。
- 食欲低下
- 嘔吐
- 下痢・軟便
- 口臭(尿毒症特有のニオイ)
- 元気がない(虚脱)
- 貧血によるふらつき
- 脱水症状
とくにステージ3の後期以降は、体内に老廃物が蓄積し、尿毒症と呼ばれる症状が現れ始めます。消化器症状や合併症が見られ、体への負担が一気に高まる時期です。
そしてステージ4まで進行すると、命に関わる状態に至ることもあるため、集中治療や入院が必要となるケースもあります。
どのような症状が見られたら受診するべき?
慢性腎臓病の症状は、進行するまでは目立たないことが多く、「食欲がない」「ぐったりしている」といったわかりやすい異変が出る頃には、すでに病状が進んでいる可能性が高いです。
明らかに異変が見られたときの受診はもちろんですが、「症状が出たら病院へ」ではなく、健康であっても定期的に健診を受けることが重要です。
慢性腎臓病は早期に発見し、早めのケアをしていくことが、病気をもちながらも長生きするための秘訣になります。
猫の慢性腎臓病の原因
ネコさんの慢性腎臓病(CKD)は、明確な原因がひとつに特定できる病気ではありません。
多くの場合、いくつもの要因が複雑に絡み合いながら、腎機能が少しずつ低下していくという進行性の疾患です。
おもな原因には、以下のようなものが挙げられます。
1.種の特性
ネコさんはもともと乾燥地帯で生きてきた動物です。そのため「水をあまり飲まず、濃縮された(尿比重が高い)おしっこを出す」といった身体のしくみを持っています。この特性が、現代の室内飼育では腎臓への負担となることもあります。
また、肉食であるネコさんは、雑食性のイヌさんと比べてタンパク質の摂取量が多い傾向があります。
その結果、腎臓の糸球体が「過ろ過(必要以上に血液をろ過する)」という状態が起こりやすくなり、長期的に糸球体が疲弊して硬くなることでネフロン(腎単位)が減少し、腎機能の低下につながる可能性があります。
2.加齢による腎機能の低下
年齢を重ねると少しずつ腎臓の細胞が減り、ろ過能力が落ちていきます。
3.遺伝的な要因
一部の猫種では、生まれつき腎臓の構造に異常がある場合があります。
4.他の病気の影響
以下のような疾患が、腎臓に二次的なダメージを与えることがあります。
- 尿石症・膀胱炎・尿路閉塞:下部尿路の異常が慢性化し、腎盂腎炎などへ波及するケースも
- 甲状腺機能亢進症:血流が増えることで腎臓の糸球体に負担がかかる可能性
また、結石や炎症のために尿路閉塞を起こして尿の逆流を招くという直接的な影響を与える場合があります。このような疾患が引き金となって、腎臓の組織にじわじわと負担が蓄積し、やがて慢性腎臓病として進行することがあります。
早期の段階で異変に気づき、適切な治療やモニタリングを行うことが大切です。
 佐藤れえ子先生
佐藤れえ子先生 ネコさんの尿にはミネラルが多く含まれており、脱水状態になると尿が濃縮されて、ミネラルが結晶化しやすくなります。結晶は尿路を傷つけたり、腎臓に悪影響を及ぼしたりするおそれもあり、尿路結石の形成につながります。
結晶をつくらないようにすることが、腎臓を守るうえでとても大切であり、そのためには、やはり脱水を防ぐことが重要になってきます。
5.食事や栄養の問題
過去には、以下のような要因が腎機能に影響を及ぼした例もあります。
- 低カリウムフードによる尿細管の輸送障害
- メラミン混入事故による腎障害
- ビタミンDの過剰添加
ただし、現在日本で流通している総合栄養食の多くはAAFCO基準に沿っており、極端な偏りは基本的にありません。
6.ワクチンや感染症に関する仮説
一部の混合ワクチンは、ウイルスを培養する際に、ネコの腎臓由来の細胞(CRFK細胞)を使用しています。
この細胞の成分に対して猫が免疫反応を起こし、「腎臓を攻撃する抗体ができる可能性があるのでは?」という指摘があります。
ただし、この説には現時点で明確な科学的根拠はありません。
また、「モルビリウイルス」というウイルスの関与が示唆された報告もありますが、ネコさんのCKDとの直接的な因果関係はまだ解明されていません。
猫の慢性腎臓病の一般的な治療法
ネコさんの慢性腎臓病は、発症してしまうと完治を目指すのは難しいですが、適切な治療によって進行を遅らせ、ネコさんの生活の質を維持することができます。
ここでは、おもな治療法を3つご紹介します。
治療法1「食事療法」

ネコさんの慢性腎臓病(CKD)では、進行のスピードをいかに抑えるかが重要なポイントです。そのために有効とされている治療法のひとつが「食事療法」です。
ステージ別・症状別に気を付けるべきポイントが異なりますが、一般的にはステージ2から腎臓病用の療法食の開始が推奨されています。
なお、ステージ1でも、検査結果によっては早めに食事の見直しが行われることもあります。
慢性腎臓病用の療法食のおもな特徴は以下のとおりです。
- リンの制限:腎臓の働きが悪くなると、リンの排出がうまくいかなくなります。リンが体内にたまると病気が進行しやすくなるため、療法食ではリンの量がしっかり制限されています。
- たんぱく質の制限:過剰なたんぱく質は老廃物の元になり、腎臓に負担をかけます。ただし、制限しすぎは逆効果なので、獣医師の指示に従ってください。
- ナトリウムの調整:高血圧を伴うネコさんには、塩分も控えめにします。
- 高カロリー設計:体重が落ちやすい腎臓病のネコさんには、少量でもカロリーがとれるごはんが望ましいです。
- 水分補給:腎臓病では脱水しやすいため、ウェットフードやスープ仕立てのごはんなどで、水分をとれる工夫が大切です。
 佐藤れえ子先生
佐藤れえ子先生 近年のフードはAAFCOなどの基準に沿って作られており、基本的には信頼できるものが販売されています。「療法食」として販売されている商品であればどれを選んでも問題ありませんので、ネコさんの好みにあわせて食べられるものを選ぶとよいでしょう。
なお、慢性腎臓病と診断されていないうちから療法食を与える必要はありません。
治療法2「皮下点滴」

慢性腎臓病のネコさんにとって、「水分をどう補うか」は非常に重要なテーマです。
もともと水をあまり飲まないネコさんは、慢性腎臓病によってさらに水分を保持しづらくなり、日常的に軽度の脱水状態になっていることも少なくありません。こうした脱水は腎臓にさらなるダメージを与え、病気を進行させる要因になります。
そのため、点滴による水分補給が必要になるケースもあります。とくに体内の水分バランスが乱れたときには、ステージ1や2の早期から皮下点滴が導入されることもあります。
さらにステージ3以降では、合併症のリスクも高まり、食欲の低下や吐き気、明らかな脱水症状などが現れやすくなり、点滴の重要性が増します。
 佐藤れえ子先生
佐藤れえ子先生 「皮下点滴をしているから安心」と思い込まず、日々の様子をよく見てあげてください。
慢性腎臓病のネコさんは、ある日を境に突然体調が悪化することもあります。その際は皮下点滴では間に合わず、静脈点滴や入院による集中治療が必要になることも。異変を感じたら、迷わず獣医師に相談しましょう。
治療法3「投薬」

慢性腎臓病のネコさんでは、症状の緩和や合併症の予防・管理のために、薬による治療が必要になることがあります。とくにステージ3の後期に差し掛かり、吐き気や貧血、高血圧など、腎臓の機能低下によって起こるさまざまな不調への対応が求められます。
おもに使われる薬の例は以下のとおりです。
| 薬の種類 | おもな目的 |
| リン吸着剤 | 食事からのリン吸収を抑え、血中リン値をコントロールする |
| カリウム製剤 | 低カリウム血症を改善する |
| 吐き気止め | 嘔吐・吐き気の症状を抑え、食欲を改善する |
| エリスロポエチン製剤 | 腎性貧血の治療(赤血球をつくるホルモンの補充) |
| 血圧降下薬 | 高血圧のコントロール |
投薬が必要なタイミングとは?
以下のような場面で、獣医師の判断により投薬が始まります。
- 血液検査で異常が出たとき(例:貧血、リン・カリウムの異常)
- 嘔吐、食欲不振などの症状が見られたとき
- 貧血や高血圧などの合併症が見られたとき
慢性腎臓病は、長期のケアが前提となるため、症状が安定しているように見える場合でも、投薬が必要になるケースがあります。
嫌がる猫に薬を飲ませるには?
薬が苦手なネコさんへの投薬は至難の業です。以下のような工夫をすることで、スムーズに与えられるかもしれません。
- ウェットフードなど嗜好性の高いフードに混ぜる
- カプセルに詰めて与える
- 投薬用のゼリーを活用する
- 寝起きのぼんやりしたタイミングを狙う など……
ネコさんにとって投薬は、大きなストレスになることが多いです。うまくいかないときは焦らず、ネコさんの性格にあった方法を少しずつ試してみてください。
試行錯誤が必要になる場面もあるかと思いますが、投薬をすることでネコさんの生活の質向上にもつながります。獣医師とも相談しながら、効果的な方法を探っていきましょう。
慢性腎臓病と診断された猫のこれから
ネコさんが慢性腎臓病(CKD)と診断されたとき、飼い主さんが最も気になるのは「これからどうなるの?」ということではないでしょうか。
慢性腎臓病は、完治する病気ではありません。しかし、早期に発見し、適切なケアを続けることで、病気の進行を遅らせることができるため、ネコさんの生活の質を維持しながら長く一緒に過ごすことも可能です。
慢性腎臓病を患った猫の余命とは
慢性腎臓病(CKD)と診断されたネコさんの余命は、診断時のステージ(進行度)や年齢、全身状態、治療やケアの内容など、さまざまな要因によって大きく異なります。そのため、「CKDと診断されたらあと〇年」と一概に言い切ることはできません。
とはいえ診断後にも、飼い主さんができることはたくさんあります。大切なのは「できるだけ早く異常に気づき、治療やケアを始めること」、そして「病気の進行を少しでもゆるやかにすること」です。
 佐藤れえ子先生
佐藤れえ子先生 慢性腎臓病は長い経過で進行し、症状が変わっていく病気です。ステージ3に進むと合併症を発症する確率がぐんと高くなります。
たとえばステージ2からステージ3に移行しようとしているところを、適切な治療と日々のケアによってぐっとこらえさせることができれば、かなりの長寿が期待できます。
「これから」のために、飼い主さんにできること

慢性腎臓病と向き合ううえで、飼い主さんの役割はとても大切です。日々の観察やケア、そして動物病院との連携を通じて、ネコさんの体調変化にいち早く気づき、必要な対応をとることができます。
以下のようなポイントを意識して、できることから始めてみましょう。
- おしっこや飲水量のチェックを習慣に 尿の色・量・回数、水を飲む量など、日々のちょっとした変化が重要なサインになります。
- ごはんの食いつきや元気さを観察 食欲不振や嘔吐、ふらつきが見られたら要注意。早めに相談を。
- 「いつもと違う」と思ったら迷わず動物病院へ 「様子を見よう」では手遅れになることも。早めの受診を心がけましょう。
- 定期的な通院・尿検査・血液検査を欠かさずに
飼い主さんの「気づき」が、ネコさんの未来を守る第一歩になります。
少しでも不安なことがあれば、ひとりで抱え込まず、信頼できる獣医師と連携して向き合っていきましょう。
腎臓病のネコさんに、飼い主ができること
慢性腎臓病(CKD)は完治が難しい病気ですが、日々のちょっとした工夫が、ネコさんの体調の安定や生活の質の維持につながります。
ここでは、家庭で飼い主さんができるケアとして「食事」と「水分管理」を中心にご紹介します。
療法食を食べてくれないときは?
慢性腎臓病の療法食は、タンパク質やリンなどが制限されており、ネコさんにとってはあまり美味しくないと感じるようです。そのため「療法食を食べてくれない」とお悩みの飼い主さんも多いことでしょう。
そのようなときは、以下のような工夫で、食いつきを改善できることもあります。
- ウェットフードを活用する
- 温めて香りを立たせる
- 通常のフードと混ぜる
- スープをかける、おやつをトッピングする など……
また、療法食にもさまざまな種類がありますから、いろいろなメーカーの商品を試してみるのもひとつの手です。食べられない期間が長く続く場合は、早めに獣医師に相談しましょう。
脱水にならないように注意
慢性腎臓病のネコさんにとって、脱水の管理は非常に重要なケアのひとつです。腎機能が低下すると尿の濃縮能力が落ち、体内の水分が失われやすくなります。
脱水はネコさんの腎臓にさらなるダメージを与えるリスクがあるため、日常的な水分補給の工夫が欠かせません。
あまり水を飲まないネコさんの飲水量を増やすために、以下のようなことができます。
- 新鮮な水を飲めるように用意しておく
- ぬるま湯など、ネコさんが好む温度を試す
- 流れる水が好きなネコさんには給水器を導入する
- ウェットフードの活用など、食事からも水分を取れる工夫を
また、脱水の兆候が見られた場合は、獣医師と相談のうえで皮下点滴(皮下輸液)を取り入れることがあります。
皮下点滴は動物病院だけでなく、自宅で行える場合もあり、ネコさんの通院ストレスを軽減できる、こまめに点滴ができるなどのメリットがあります。
自宅と動物病院での点滴の違い
| 実施場所 | 実施者 | 点滴の種類 | メリット |
| 自宅 | 飼い主さん(獣医師の指導あり) | 皮下点滴 | ・ネコさんの通院ストレス軽減・こまめに点滴できる・経済的負担が抑えられる |
| 動物病院 | 獣医師 | 皮下点滴、静脈点滴 | ・状況に応じた治療対応が可能・急変時の即時対応ができる・ビタミン等の補給もできる(静脈点滴) |
▼ネコさんの自宅皮下点滴に関する詳しい記事はこちら
▼皮下点滴アンケート結果はこちら

nekozuki独自に調査したアンケートでは、44%の人が「自宅での皮下点滴経験あり」と回答。さらに自宅での皮下点滴経験者の56%が「皮下点滴は難しい」と回答、もっとも難しかったこと第1位は「保定」でした。
このような飼い主さんのお悩みを解決するべく、nekozukiでは皮下点滴補助具「ねこずきのおくるみ」を開発しました。詳しくは次の見出しでご紹介します。
猫の保定をスムーズにして皮下点滴を習慣化「ねこずきのおくるみ」

「ねこずきのおくるみ」は、慢性腎臓病(CKD)などで定期的な皮下点滴が必要なネコさんと飼い主さんのために開発した、飼い主さん一人でも安全かつスムーズに保定できる、“着せる保定服” です。
一人でも安心して皮下点滴が可能に
自宅での皮下点滴は、ネコさんの動きを制御する「保定」が難しく、とくに一人暮らしの飼い主さんにとっては大きな課題です。
「ねこずきのおくるみ」は、ネコの習性を活かした設計で、飼い主さん一人でもネコさんを安全に保定し、皮下点滴を行うことができます。
猫の習性を活かしたデザイン

ネコさんは「前足が地面についていると安心する」習性があります。この習性を活かし、「ねこずきのおくるみ」は前足を出した状態で着用できるデザインとなっており、ネコさんがリラックスしやすくなっています。
シャツのように包み込む構造で、ネコさんのストレスを軽減しながら保定が可能です。
使いやすさと安全性を兼ね備えた設計

このほか「ねこずきのおくるみ」は、以下のような特徴を備えています。
- 肩甲骨部分の開口部:皮下点滴の針を刺しやすいように設計されています。
- サイズ調整が簡単:マジックテープ付きの腹巻きとベルトで、ネコの体型に合わせて調整できます。
- ファスナーにもひと工夫:ネコさんの毛が挟まらないよう、ファスナーを保護する耳をつけています。
- 撥水性のある生地:薬品による濡れを防ぎ、軽量で丈夫な素材を使用しています。
- 丸洗い可能:家庭で洗濯できるため、常に清潔に保てます。
\特許を取得しました/
 太野
太野 「ねこずきのおくるみ」は、自身の愛猫が腎不全を患った経験から生まれました。通院のストレスを減らし、自宅でのケアを可能にすることで、ネコさんと飼い主さんの負担を軽減したいという想いが込められています。
100回以上の試作とテストを重ね、“ネコの習性を活かしたデザイン” が完成しました。
「ねこずきのおくるみ」はネコ社員の協力により生まれた製品です。
ネコさんと一緒に開発した「ねこずきのおくるみ」でネコさんの自宅での皮下点滴が身近なものとなり、ネコと飼い主さんの闘病生活を少しでも快適なものとなるようサポートし、ふれあいの時間が増えることを願っています。
▼「ねこずきのおくるみ」開発秘話の詳細はこちら

ねこずきのおくるみ
「入れる」保定袋から「着せる」保定服へ。ネコのストレスを軽減し、飼い主さん一人でも保定できる、特許技術のネコ用保定袋。
詳細はこちら
猫の慢性腎臓病を予防するには?

ネコさんの慢性腎臓病(CKD)は、日常のちょっとした工夫で発症リスクを軽減することができます。ここでは、愛猫のために飼い主さんができる5つの予防習慣をご紹介します。
水をたくさん飲める環境をつくる
ネコさんはもともと砂漠地帯にルーツを持つ動物で、水をあまり飲まない性質があります。そのため濃縮された尿を出しやすく、腎臓に負担がかかりやすいといわれています。
腎臓病を予防するためには、十分な水分補給が欠かせません。飲水量を増やすには、以下のような工夫が有効です。
- 常に新鮮な水を用意する
- ネコさんが好む水温(人肌程度)で与える
- 流れる水が好きな子には自動給水器を設置する
- ウェットフードやスープなどを与える
「水を飲まないから仕方ない」とあきらめず、ネコさんの“好み”を探っていき、水分補給を習慣化しましょう。
尿のチェックを習慣にする
腎臓の異常は、尿の状態にいち早く現れることがあります。とくに、尿量・色・回数の変化は見逃せません。
- 透明に近い色の薄い尿が増えた
- いつもよりトイレの回数が多い/少ない
- 色が濃く、ニオイも強くなった など
こうした小さな変化を見逃さないために、日常的にネコさんの尿を観察する習慣をつけることが大切です。白い紙タイプの猫砂など、色の変化がわかりやすいトイレを活用するのもおすすめです。
猫ドックを受ける
ネコの慢性腎臓病は、初期ではほとんど症状が出ないものです。そのため、目に見える症状が現れる頃にはすでに病状が進行しているケースが少なくありません。
慢性腎臓病のキーワードは「進行を遅らせる」こと。予防の観点からも、年に1回の「猫ドック(健康診断)」を受けることが非常に重要です。
とくに、腎臓に関心のある獣医師のいる病院では、より詳しく腎機能をチェックできる項目が含まれていることもあります。
症状が出てからの対処ではなく、早期発見・早期対応が「長く元気に暮らすための第一歩」です。
トイレ環境を見直す
トイレ環境が不快だと、ネコさんは排尿を我慢してしまい、膀胱炎や尿路疾患の原因になることがあります。そしてこれが慢性腎臓病の引き金になるケースも否定できません。
いま一度、以下のようなポイントをチェックし、トイレ環境を見直してみましょう。
- 十分な数のトイレを設置しているか(目安はネコの数+1)
- トイレが清潔に保たれているか
- トイレの場所にストレスを感じる要因(人通り・騒音・他猫など)がないか
- ネコの好みに合ったトイレや猫砂を使っているか
とくに多頭飼育の場合は、グループごとにトイレを分けるなどの工夫も有効です。ネコさんにとって「安心できるトイレ環境」を整えることが、予防の第一歩になります。
“身近なリスク”をなくす
私たちが日常的に使う製品や身の回りの環境が、知らずのうちにネコさんの腎臓に負担をかけている可能性もあります。以下に身近なリスクの一例を挙げています。
- 飲み水の質に注意
古い配管や硬水、ミネラルの多い水は要注意。基本的には日本の水道水で問題ありませんが、念のため浄水器を使うのも一案です。 - 給水ボトルの使用に注意
給水ボトルは飲みにくく、飲水量が不足しがちです。できれば給水ボトルの使用は避け、ネコさんがたっぷり水を飲めるような器を使うのが望ましいでしょう。 - ユリ科の植物に注意
ユリはネコさんにとって猛毒です。ネコさんが舐めてしまうと急性腎障害の原因になることも。多様な種類があるうえ、ユリ科以外の植物にもネコにとって危険なものがあるため、観葉植物は部屋に飾らないようにしましょう。
「ちょっとくらい大丈夫」が、大きなリスクにつながることも。ネコさんの健康のために、今一度“身近なリスク”を見直してみてください。
【Q&A】猫の慢性腎臓病について

最後に、ネコさんの慢性腎臓病に関するよくある質問をQ&A方式でご紹介します。
Q1.腎臓病の検査にはどのようなものがありますか?
A.慢性腎臓病(CKD)の診断には、以下のような検査が重要です。
- 血液検査:クレアチニン、BUN、SDMAなどの腎機能マーカーを確認します。特にSDMAは早期発見に役立ちます。
- 尿検査:尿比重、蛋白尿(UPC)などをチェックし、腎臓の状態を把握します。
- 画像検査:超音波検査やレントゲンで腎臓のサイズや構造の異常、結石の有無などを調べます。
なお、慢性腎臓病のステージ分類は、クレアチニン値とSDMAで行われています。ただし、すべてのケースで有効な数値ではなく、たとえばもともとSDMAが高い猫種がいたり、リンパ腫の場合にSDMAが高くなる傾向が見られたりと、例外もあります。
そのため、クレアチニンとSDMA以外にも、尿検査やエコー、触診などの検査から総合的に診断して、そのうえでIRISのガイドラインに基づいたステージ分類が行われるのです。
Q2.ネコの慢性腎臓病が治ったということはありますか?
A.残念ながら、慢性腎臓病(CKD)は完治が難しい病気です。一見数値がよくなったように見えても、“腎臓病が治った”ということにはつながりません。
しかし、早期発見と適切なケアにより進行を遅らせることができるため、生活の質(QOL)を保ちながら長く付き合っていくことは可能です。なお、急性腎障害は、原因を取り除き適切な処置をすることで治癒が見込めます。
Q3.慢性腎臓病の初期に気づくことはできますか?
A.初期の慢性腎臓病は症状が目立ちにくいのが特徴で、とくにステージ3の初期~中期ごろまでは臨床症状が見られないことが多いです。
わずかな変化を捉えるとすれば、ネコさんの飲水量や尿の状態に注目することが大切です。「水をよく飲むようになった」「水のように薄い、色のない尿」ということは、腎臓での水の再吸収が低下したために薄い尿(低比重尿)が出ているということです。そのために水をたくさん飲むようになったのです。
また、定期的に健康診断を受けることも早期発見に役立ちます。
Q4. なぜネコに腎臓病が多いのですか?
A.ネコさんは、もともと乾燥地帯で暮らしていた動物が祖先のため、水をあまり飲まなくても生きられるような体のしくみをしています。そのため、おしっこが濃くなりやすく、腎臓に負担がかかりやすいという特徴があります。
また、ネコさんは高タンパクな食事に適応した体をしているため、代謝の過程でも腎臓に負荷がかかりやすいと考えられています。さらに、加齢や遺伝的な体質、尿路結石や尿閉などの病気が腎臓に影響を及ぼすケースもあります。
近年ではネコの寿命が延びたことで、腎臓病になるネコさんがとても多く見られるようになっています。
Q5.AIMって何ですか?
A.AIM(Apoptosis Inhibitor of Macrophage)は、東大の研究チームが“腎臓病に関係する可能性のある物質”として研究しているタンパク質です。
現在、AIMに着目したキャットフードなども出ていますが、効果についてはまだエビデンスが確立されていない段階です。研究は進められており、今後の成果に期待が集まっています。
Q6. 腎臓病はワクチンで起こることがあるのですか?
A.混合ワクチンでは、ネコの腎臓由来の細胞が製造過程で使われており、その成分に対して免疫反応が起こる可能性があるのではないかという仮説が示されています。
ただし、科学的な根拠は確立されていないため、現時点では明確な因果関係は明らかになっていません。
Q7.猫ドックは何歳から行くのがよいですか?
A.ネコさんは少なからず先天性の疾患を持っている場合があるため、「まだ1歳だから大丈夫」などということはなく、生まれてすぐの頃から年に1回のペースで受診できると安心です。
また、気の合う獣医師を見つけることもひとつです。何かあったときには経過やネコさんの様子を見ながら根気よく治療やケアの方法を一緒に探ってもらえるような、腎臓に関心がある先生と付き合っていけることも大事なことだと思います。
まとめ
ネコの腎臓病、とくに慢性腎臓病(CKD)は、高齢ネコをはじめ、ネコさんに多く見られる病気です。初期にはほとんど症状が出ないこともあり、「もっと早く気づいていれば」と悔やむ飼い主さんも少なくないでしょう。
しかしながら、早期に発見し、適切なケアを続けることで進行を遅らせ、ネコさんの生活の質を保つことができます。そのために、今日からできることはたくさんあります。
- たっぷり水を飲める環境を整える
- 日々の尿をチェックする習慣をつける
- 信頼できる獣医師と連携し、定期的な健診(猫ドック)を受ける
また慢性腎臓病の治療では、ネコさんを慢性的な脱水症状にさせないために獣医師と相談のうえ、自宅で皮下点滴を行うこともあります。
その際に多くの飼い主さんが課題としているのが「保定」です。ネコさんをやさしく保定できる「ねこずきのおくるみ」は、ご自宅での皮下点滴を無理なく続けるためのサポートアイテムとしてご活用いただけます。
慢性腎臓病は「治す」ではなく「症状を進行させない」ことが大切です。
ネコさんの小さな変化を見逃さず、毎日のケアを丁寧に重ねていくことで、長く穏やかな時間をともに過ごしていけることを願っています。
ネコさんの保定にお困りの飼い主さんへ。

ねこずきのおくるみ
「入れる」保定袋から「着せる」保定服へ。ネコのストレスを軽減し、飼い主さん一人でも保定できる、特許技術のネコ用保定袋。
詳細はこちら